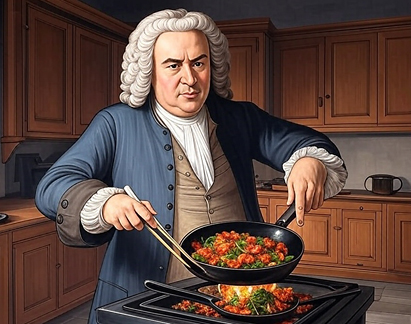●29日は思い立って豊田市へ日帰り遠征。朝早くに家を出て、豊田市美術館と豊田スタジアムを巡る作戦。この行程はこれで3度目なので新味はないのだが、豊田スタジアムは競技場として最高である上に、建築物としても美しいので訪れる価値がある。前回は豊田大橋(スタジアムとともに黒川紀章の設計)から歩いて向かったが、今回は別ルートで久澄橋を通って向かう。座席がバックスタンドだったので、こちら側から入るともしかしたら近いのではと勝手に期待したが、ぜんぜんそうではなく、入場口は同じだった。

●これまでは3階席だったが、今回はバックスタンドの2階席。たぶん、ここが最上のエリアでは。反対側のメインスタンドの2階席中央がVIPエリアっぽくなっている。3階も2階も急勾配なので、とても見やすい。さすがの球技専用競技場。

●観客数は34151人。アウェイ側にも大勢の柏サポがつめかけていた。往復には豊橋停車の新幹線ひかり(本数は少ない)を使ったが、行きも帰りも柏サポをたくさん見かけた。なんなら首都圏在住と思しき名古屋サポもいる。Jリーグでは観光とセットなった独自のアウェイツーリズムが発達していると言うが、まさにそれを実感。定時運行前提の高速鉄道網があるからこそ可能な文化だろう。

●で、試合は長谷川健太監督率いる名古屋が開始わずか2分で稲垣祥のゴールで先制。リカルド・ロドリゲス監督の柏は劣勢だったが、前半に山田雄士のゴールで追いつき、後半5分に細谷真大が逆転ゴールを決めてこれが決勝点に。同じ3バックだが攻撃に手数をかけない名古屋に対して、柏はキーパーからボールをつなぐリスクをとるスタイル。キーパーとセンターバックの危なっかしいパス回しが、かつてのポステコグルー時代初期のマリノスをほうふつとさせる。これは選手のターンオーバーの影響があったかもしれないのだが、あまりうまく機能しているようには見えない。数少ないチャンスにゴールが決まったという印象。内容的には名古屋が勝っていたと思う。名古屋 1-2 柏。柏はこれで2位に浮上、名古屋は下から2番目の19位。その名古屋より下にいる唯一のチームがマリノスだ。トホホ……。親会社がトヨタと日産で残留争いとは。